2021年正月以降ブログの更新が滞っている。新型コロナ情報の渉猟を続けていたが、コロナの話題にやや疲れてしまったこともある。さらに2月、3月、4月とネットワーク講演、いわゆるWebinar (Web Seminar)があり、コロナの情報や耳鼻咽喉科感染症の情報提供を行っていたが(センターの活動参照)、コロナの第3波、第4波とコロナの攻撃にやや疲労気味であった。この疲れを和らいでくれる情報を提供したくなった。
米国ディーリア・オーエンズ著の「ザリガニの鳴くところ」は、コロナ禍で疲れた心をいやしてくれる小説だ。実は昨年の3月に購入してすでに読んだが、最近また読みたくなり今度はAudibleで朗読を聴いている。これがすこぶる良い。朗読で聴くのはだいぶ前に川端康成「雪国」でとりこになったが、本当に良い小説を耳で聴くのは脳にとても心地よい。
この小説は社会派小説であり、恋愛小説であり、推理小説でもある。さらにこの小説は70歳にして小説家デビューした老女の処女作である。
自然の描写が実に生き生きとしており美しいが、作者が米国の著明な生物学者であり、湿地で暮らしていた作者の実体験を基にしているという後書きから、なるほどと伺える。
湿地の奥地で一人で生きてきた少女カイアがこの小説の主人公だ。1950年代、まだ学校にも行かない幼小児のころに家族が次々と去り、最後に残っていた暴力をふるう父親も彼女を置き去りにする。「貧乏人」が世間から隠れるように住む湿地の奥で、カイアという呼び名だけで本名すら当初はわからない。母から教わったわずかな家事の知恵を頼りに生き抜く生活は激しく孤独で痛ましく、その絶望が伝わってくる描写が生々しく心に響く。
本小説はミステリーの要素を含んでおり、殺人の犯人捜しも同時進行していくが、何が正義で何が悪とか、そのような評価は重要なものではなく、
「生きるとは……」 「生き残るとは……」 「生存本能とは……」 、
というとても大きなテーマを包含している。
どんな境遇にあっても自分自身の力で人生を切り拓いていくことができるのだという意志が書かれている。
自然を頼りに動物や植物と対話しながら生きる少女は、兄の友人だった少年に文字を教わる。言葉を知り、本を読み、自分の体で経験し、それを言葉で表すことを知った彼女は、誰よりも湿地の自然を理解するのだ。その過程で、よりどころになるのは言葉だ。自分を安らかにしてくれる唯一のものである自然への思いや孤独に共鳴する詩が、小説のあちこちに引用されている。
コロナ禍で言葉による会話が激減し、心が疲れているときに癒やしてくれる涼風になると請け合う。是非一読を勧める。
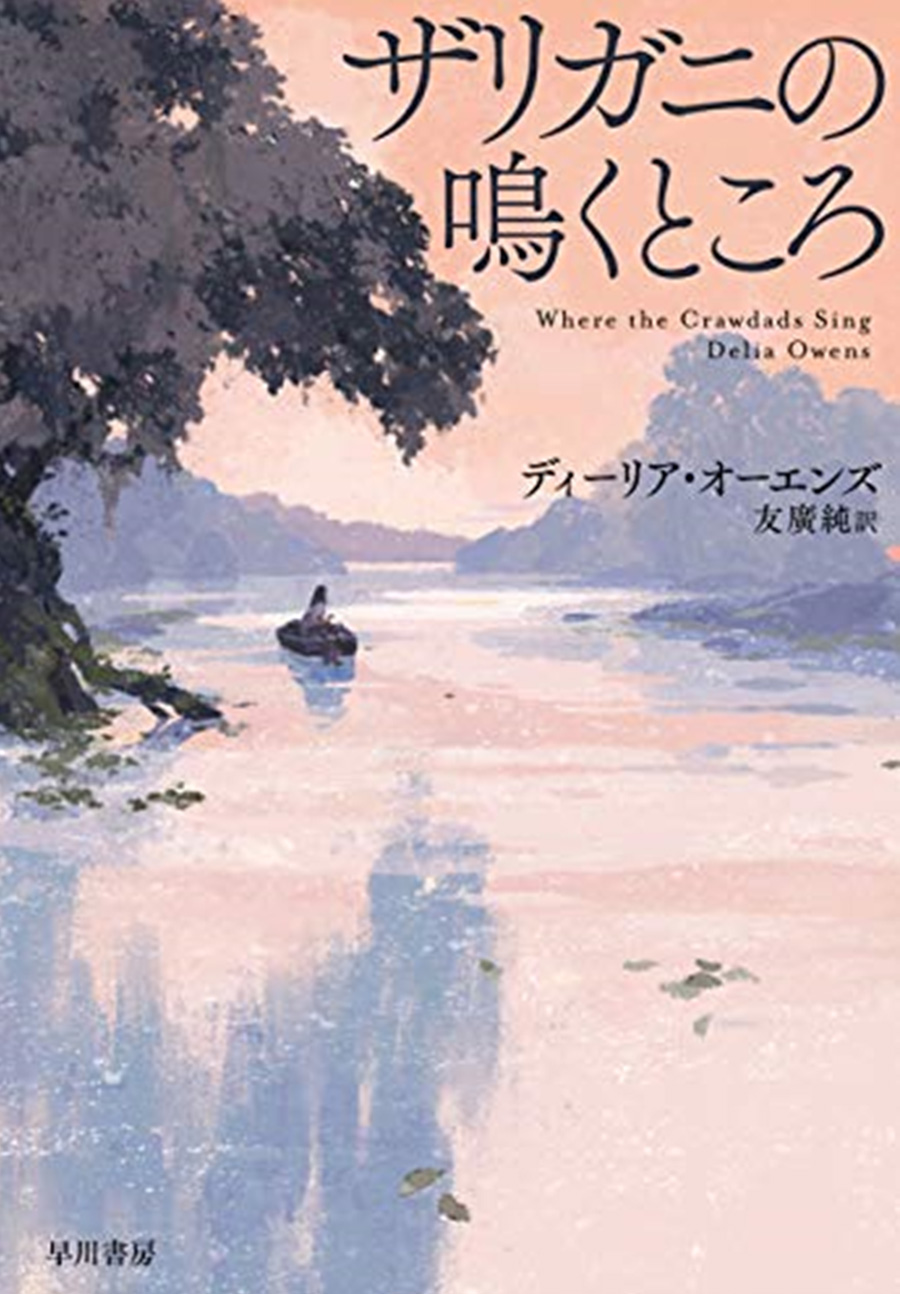
ディーリア・オーエンズ著 友廣純(翻訳) 早川書房

